河野 龍太郎 Weekly Economic Report

著書のご案内
『世界経済の死角』
河野龍太郎
唐鎌大輔
幻冬舎より2025年7月30日に発売されました。
全国の書店およびオンラインストアでお求めください。
Amazon Rakutenブックス ほか
※リンクは新しいウィンドウで開きます
- 序章 外国人にとって“お買い得な国”の裏側
- 第1章 なぜ働けどラクにならないのか
- 第2章 トランプ政権で、世界経済はどう変わる?
- 第3章 為替ににじむ国家の迷走
- 第4章 日本からお金が逃げていく?
- 第5章 AIと外国人労働者が日本の中間層を破壊する?
- 最終章 変わりゆく世界
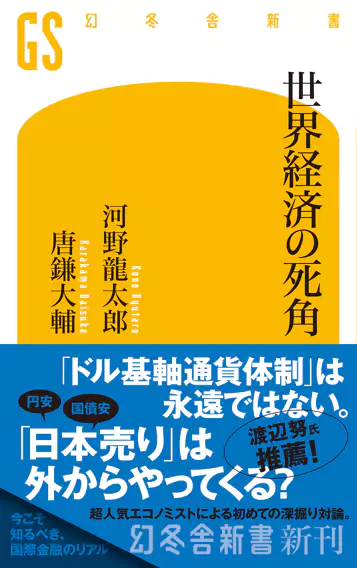
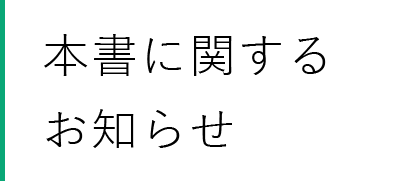
<エコノミストが選ぶ2025年の経済図書べスト10>に選出されました
日本経済新聞 | 2025年12月27日 朝刊
書評をいただきました。ありがとうございます。
- 軽部 謙介 氏 (ジャーナリスト、帝京大学教授) | 山形新聞 2025年10月12日
- 早川 英男 氏 (富士通エグゼクティブアドバイザー) | 週刊金融財政事情 2025年9月30日
- 入山 章栄 氏 (早稲田大学大学院経営管理研究科教授) | 日本経済新 2025年9月25日 夕刊
- 平山 賢一 氏 (麗澤大学教授) | 週刊エコノミストOnline 2025年9月12日
- 佐橋 亮 氏 (国際政治学者 東京大学教授) | 読売新聞 2025年8月31日 朝刊
『日本経済の死角:収奪的システムを解き明かす』
筑摩書房より2025年2月7日に発売されました。
全国の書店およびオンラインストアでお求めください。
筑摩書房 Amazon Rakutenブックス 紀伊國屋書店 ほか
※リンクは新しいウィンドウで開きます
本書の内容を紹介した「はじめに」をお読みいただけます(PDF 約1MB)
- 第1章 生産性が上がっても実質賃金が上がらない理由
- 第2章 定期昇給の下での実質ゼロベアの罠
- 第3章 対外直接投資の落とし穴
- 第4章 労働市場の構造変化と日銀の二つの誤算
- 第5章 労働法制変更のマクロ経済への衝撃
- 第6章 コーポレートガバナンス改革の陥穽と長期雇用制の行方
- 第7章 イノベーションを社会はどう飼いならすか
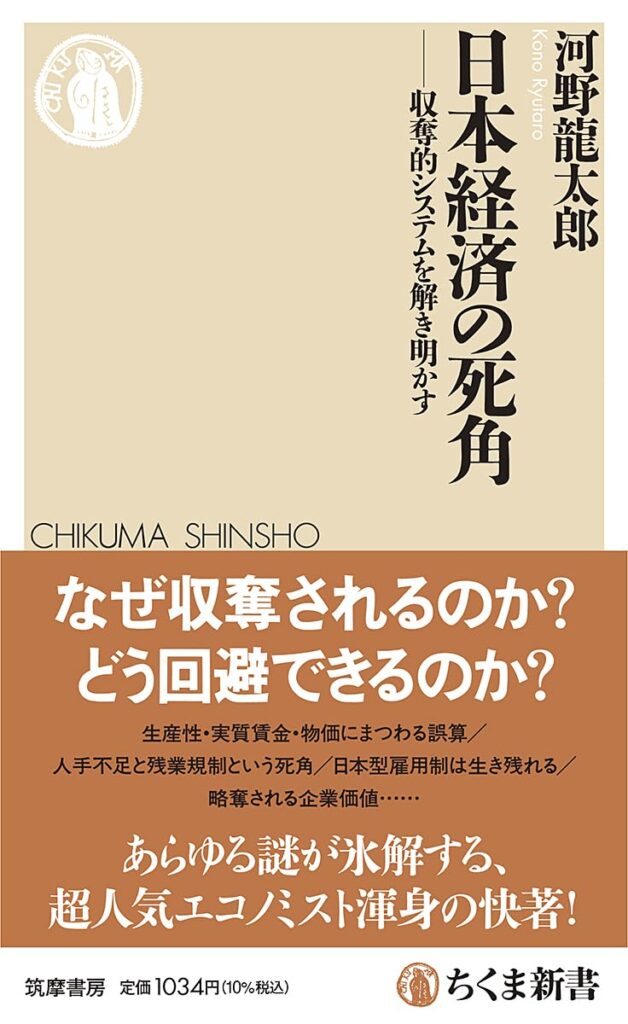
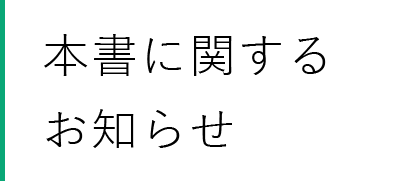
【8位受賞のお知らせ】
中央公論社<「新書大賞2026」> 8位に選出されました
中央公論社 | 2026年2月10日
【1位受賞のお知らせ】東洋経済 <有識者が選ぶ「ベスト経済書2025」> 1位に選出されました
東洋経済 | 2025年12月20日
【ノミネートのお知らせ】
筑摩書房 <第34回「山本七平賞」>にノミネートされました
筑摩書房 | 2025年8月27日
書評をいただきました。ありがとうございます。
- 小玉 祐一 氏 (明治安田総合研究所 チーフエコノミスト) | 週刊金融財政事情2025年6月3日
- 藻谷 浩介 氏 (株式会社日本総合研究所 主席研究員) | 毎日新聞 2025年5月3日 朝刊
- 諸富 徹 氏 (京都大学大学院教授) | 週刊エコノミスト Online 2025年5月2日
- 白川 方明 氏 (元日本銀行総裁) | ちくまWeb 2025年3月3日
- 吉田 徹 氏 (同志社大学教授) | SYNODOS 2025年2月19日
『グローバルインフレーションの深層』
慶応義塾大学出版会より2023年12月15日に発売されました。
Amazon、楽天ブックス、Honto、ほか全国の書店にてお求めください。
本書の内容を紹介した「はじめに」をお読みいただけます。(PDF 約2MB)
- 2024年 ベスト経済書・経営書 第5位 – 週刊東洋経済
目次
第1章 1ドル150円台の超円安が繰り返すのか
第2章 グローバルインフレの真因
第3章 グローバルインフレは財政インフレなのか
第4章 構造インフレ論、中国日本化論、強欲インフレ論
第5章 日本がアルゼンチンタンゴを踊る日
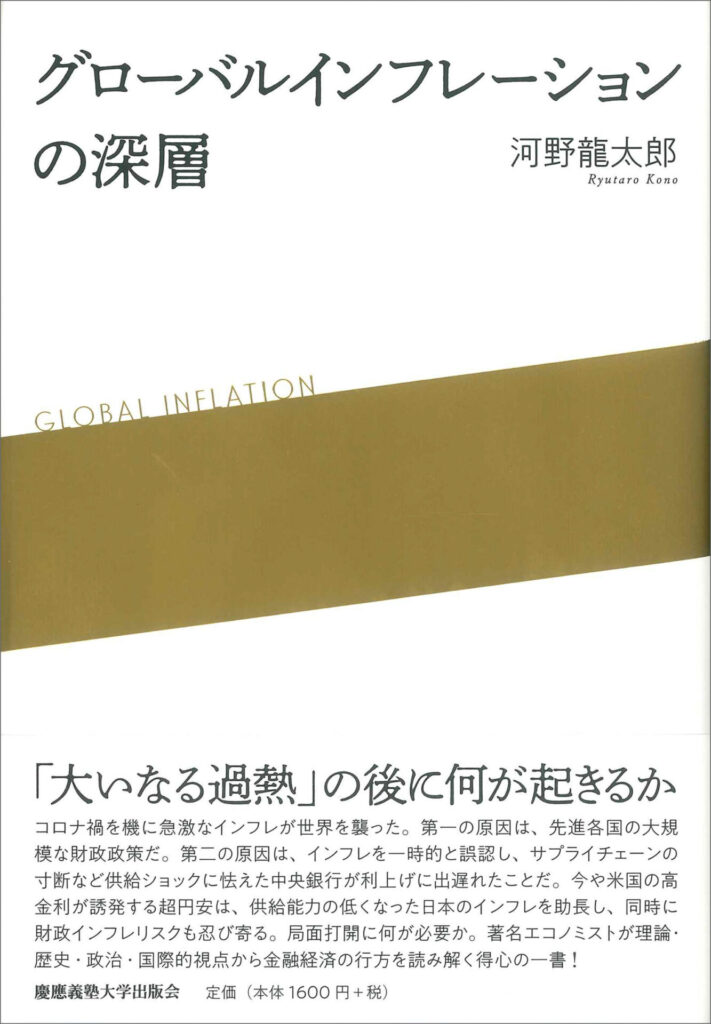
『成長の臨界 「飽和資本主義」はどこへ向かうのか』
慶應義塾大学出版会 2022年7月15日発売
「はじめに」(PDF: 約0.6MB)
Amazon、楽天ブックス、ほか全国の書店にてお求めください。
- エコノミストが選ぶ 経済図書ベスト10(2022年)第9位 – 日本経済新聞
- 2022年 ベスト経済書 日本の活路の指針として支持を集めた書籍 第1位 – 週刊ダイヤモンド
- 2022年 ベスト経済書・経営書 第2位 – 週刊東洋経済
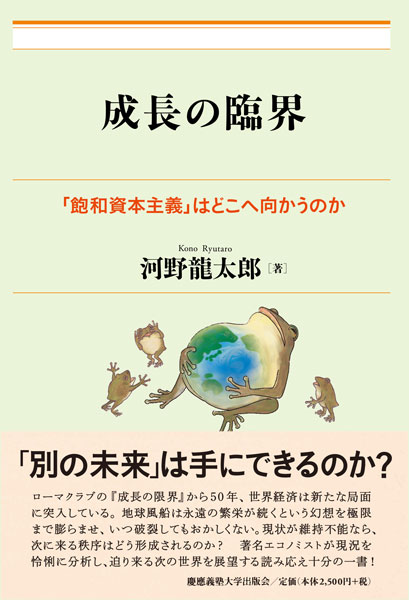
出演動画のご紹介
宮﨑知己の考えるラジオ《THINK RADIO》「日本経済の死角を衝く」
2回目は、年明け以降の世界経済の行方と、この度の総選挙後の日本経済の行方について検証しました。
秋葉原のスタジオにお招きいただき、1回目は日本だけ実質賃金が上がらない理由についてお話させていただきました。
日経チャンネル「包摂的イノベーションとは何か」
2025年9月29日に開催されたシンポジウム「Smart Work-X 2025 人的資本経営への挑戦~だれもが健康で、働きたいだけ働ける社会へ~」に登壇しました。その際の講演を動画で視聴できます。(約30分)
ReHacQ−リハック−【公式】YouTubeに出演しました
「あつまれ!経済の森」で唐鎌大輔氏、後藤達也氏とご一緒させていただきました。
2025年3月に日本経済の停滞についてお話しさせていただいた動画はこちらです 前編|後編
東洋経済オンライン 公式YouTubeチャンネル
日本経済と世界経済の先行きについてお話させていただきました。(収録日: 2025年9月18日)
2025年4月のトランプ関税とグローバル経済についての動画はこちらです。
PIVOT公式YouTubeチャンネル
みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏とご一緒し、最近のアメリカ経済および日本経済について対談させていただきました。(収録日: 2025年8月4日)
文藝春秋PLUS 公式YouTubeチャンネル
第二次トランプ政権が世界経済にもたらす影響についてお話させていただきました。
2025年4月には「日本の実質賃金が上がらない理由」というテーマでお話させていただきました。前編|後編
TBS CROSS DIG with Blomberg 「Economic Labo」
YouTubeチャンネル「TBS CROSS DIG with Blomberg」に出演し、みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏と対談させていただきました。(収録日: 2025年7月17日)
唐鎌大輔氏とは2025年2月にもご一緒させていただきました。前編|後編
最近のレポート
BNPパリバ証券 河野龍太郎 : 減税ポピュリズムへの適切な処方箋 -現役世代の低中所得世帯に冷たい日本の社会構造-
No.1120 (2026年2月20日)
拡張財政で総需要を刺激しても、ほぼ完全雇用にある日本では、実質GDPはさほど増えず、物価上昇圧力が高まるだけだ。この3年、筆者はそう繰り返してきた。2022年10-12月に593.7兆円だった名目GDPは、2025年10-12月には668.9兆円と12.7%(75.2兆円)も膨らんだが、実質GDPは2022年10-12月の584.0兆円から、2025年10-12月は589.7兆円とわずか1.0%(9.7兆円)の増加に留まる。高圧経済戦略で、名目GDPが膨らんでも、供給制約によって、物価ばかりが上昇し、実質GDPはさほど増えない構造にあるのだ。
もちろん、インフレ・タックスと金融抑圧によって、家計から政府に多大な所得移転が生じているのだから、一定程度、それを調整する必要があると考える人もいるだろう。ただ、経済が完全雇用にあるのだから、規模を追求してはならない。困窮する人に的を絞った物価高対策とする必要がある。総選挙でチームみらいを除く各党が消費税減税を掲げたのは、無謀と考える人もいるだろう。まさに総選挙は、減税ポピュリズムの極みでもあった。
ただ、日本には減税ポピュリズムが沸き上がるもっともな理由が存在することも認識しておく必要がある。端的に言えば、日本は、現役世代の低所得世帯や子育て中の低中所得世帯に極めて冷たい社会構造となっているのだ。その処方箋の一つは、消費税減税の後継として高市早苗政権が位置付ける「給付付き税額控除」である。なぜ、給付付き税額控除が処方箋になるのか、以下、詳しく論じる。
全文はこちらをクリックしてご覧ください
PDF (約1MB) *新しいウィンドウが開きます
BNPパリバ証券 河野龍太郎 : 蘇る「覇権なき無秩序」とバンコール -ブレトンウッズの攻防と民主的通貨体制というレトリック-
No.1119 (2026年1月9日)
新たな国際通貨体制に関する論議で「バンコール」という言葉が出てくると、多くの人はこう反応する。「理想的だが、現実的ではなかった通貨構想」と。確かにバンコールは実現しなかった。しかし、それを単なる空論として片付けてしまうと、私たちは重要な論点を見落としてしまう。なぜ、それが実現しなかったのか。そして、なぜ今になって再び語られるようになったのか。この問いに答えるためには、戦後のIMF体制の起点となった1944年のブレトンウッズ会議に立ち返る必要があるだろう。
第一次世界大戦後の国際通貨秩序は、大混乱の連続だった。戦前の国際金融体制を支えていた金本位制は崩れ、各国は通貨切り下げによって、自国経済を守ろうとした。為替レートは経済戦争の武器となり、貿易はブロック化に向かい、世界経済は分断されていった。重要なのは、1930年代に、世界経済に訪れたショックを吸収するためのグローバル公共財を供給する主体、すなわち「覇権国」が不在だったことだろう。
全文はこちらをクリックしてご覧ください
PDF (約1MB) *新しいウィンドウが開きます
BNPパリバ証券 河野龍太郎 : 年末年始の推薦図書
No.1118 (2025年12月18日)
今週のトピックは、恒例となりました年末年始の推薦図書です。夏以降に読んだものの中から、6冊をご紹介します。
『コロナ対策の政策評価 日本は合理的に対応したのか』岩本康志著、慶応義塾大学出版会
『とてつもない特権 君臨する基軸通貨ドルの不安』バリー・アイケングリーン著、小浜裕久監訳 勁草書房
『アメリカの新右翼 トランプを生み出した思想家たち』井上弘貴著 新潮社
『新しい階級社会 最新データが明かす〈格差拡大の果て〉』橋本健二著 講談社現代新書
『大不況下の世界1929-1939改訂増補版』チャールズ P.キンドルバーガー著 石崎昭彦訳、木村一朗訳 岩波書店
『緊縮資本主義 経済学者はいかにして緊縮財政を発明し、ファシズムへの道を開いたのか』クララ・E ・マッテイ著、中野剛志解説、井坂康志訳 東洋経済新報社
‥‥
以下もお薦めです。
『いまどうするか日本経済』脇田成著 筑摩書房
『エブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」』エミン・ユルマズ著 文藝春秋
『金融政策の効果測定 銀行理論と因果推論による再検証』郡司大志著 慶應義塾大学出版会
『コメ高騰の深層 JA農協の圧力に屈した減反の大罪』山下一仁著 宝島社
『自由と国家 繁栄する国 衰退する国(文庫版 上・下)』ダロン・アセモグル著、ジェイムズ・A・ロビンソン著、櫻井祐子訳 早川書房
『消費税と政治 財政再建をめぐる理念と思惑』上川龍之進著 有斐閣
『税の日本史』諸富徹著 祥伝社
『強い日本を残す 円安と闘った男がすべてを語る』神田眞人著、 清水功哉( 聞き手)日経BP 日本経済新聞出版
『2075 次世代AIで甦る日本経済』岩田一政編集、日本経済研究センター編集 日経BP 日本経済新聞出版
『ノスタルジアは世界を滅ぼすのか ある危険な感情の歴史』アグネス・アーノルド=フォースター著、 月谷真紀訳 東洋経済新報社
『フランスの右派 1815-1981』ルネ・レモン著 大嶋厚・中村督・吉田徹訳 岩波書店
『未完の名宰相 松平定信』大場一央著 東洋経済新報社
全文はこちらをクリックしてご覧ください
PDF (約1MB) *新しいウィンドウが開きます
関連リンク
日経ヴェリタス「債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」エコノミスト部門2位、債券アナリスト部門10位を獲得

「成長の臨界」を考えるためのえりすぐりの書籍を紹介しています
