河野 龍太郎 Weekly Economic Report

Photo by Kazutoshi Sumitomo
『グローバルインフレーションの深層』発売のお知らせ
慶応義塾大学出版会より2023年12月15日に発売されました。
Amazon、楽天ブックス、Honto、ほか全国の書店にてお求めください。
本書の内容を紹介した「はじめに」をお読みいただけます。(PDF 約2MB)
目次
第1章 1ドル150円台の超円安が繰り返すのか
第2章 グローバルインフレの真因
第3章 グローバルインフレは財政インフレなのか
第4章 構造インフレ論、中国日本化論、強欲インフレ論
第5章 日本がアルゼンチンタンゴを踊る日
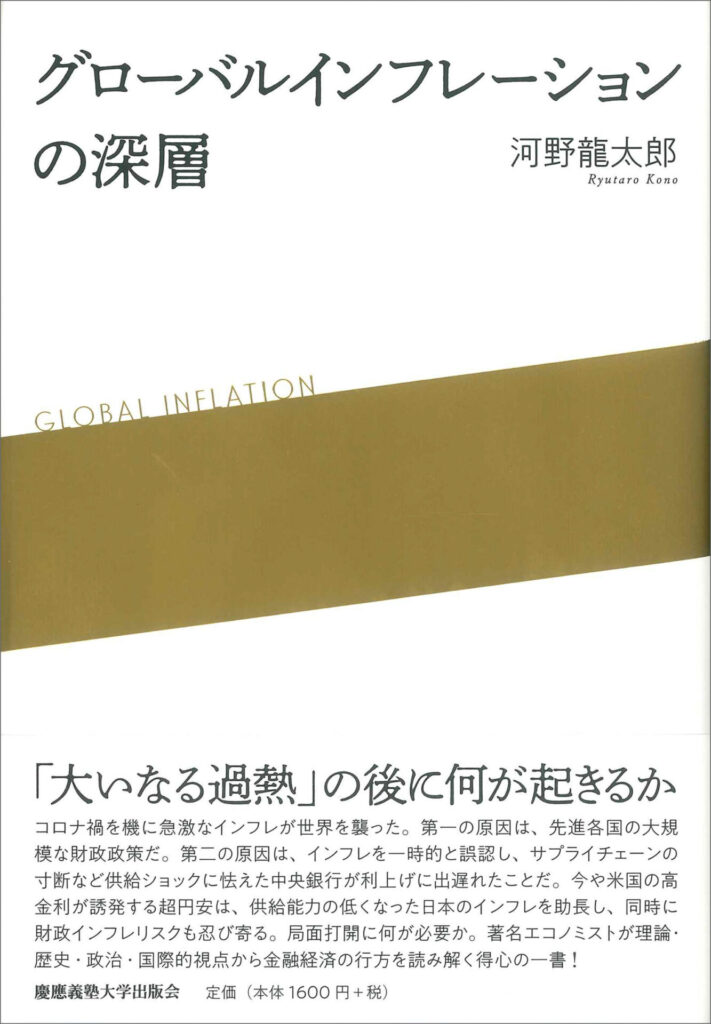
『成長の臨界 「飽和資本主義」はどこへ向かうのか』
慶應義塾大学出版会 2022年7月15日発売
「はじめに」(PDF: 約0.6MB)
Amazon、楽天ブックス、ほか全国の書店にてお求めください。
- エコノミストが選ぶ 経済図書ベスト10(2022年)第9位 – 日本経済新聞
- 2022年 ベスト経済書 日本の活路の指針として支持を集めた書籍 第1位 – 週刊ダイヤモンド
- 2022年 ベスト経済書・経営書 第2位 – 週刊東洋経済
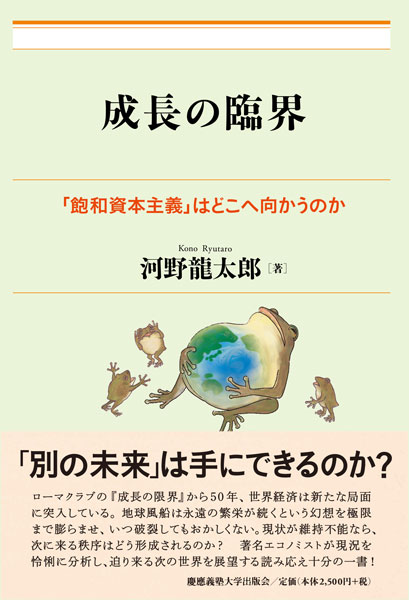
ReHacQ−リハック−【公式】YouTubeに出演しました
円安が続いている原因や日本が抱えている労働市場の問題についてお話させていただきました。
最近のレポート
BNPパリバ証券 河野龍太郎: トランプ勝利の米金融政策へのインプリケーション -利下げ継続は可能なのか-
No.1061 (2024年7月19日)
共和党は7月15日に開幕した全国党大会でトランプ氏を大統領候補として正式決定した。同時に、副大統領候補として、ラストベルトに住む白人中流家庭の没落を描いた「ヒルビリー・エレジー」で知られる上院議員のJ・D・バンス氏を副大統領候補に正式決定した。共和党は13日のトランプ狙撃事件を受けて党内の結束が一段と強まる一方、民主党はテレビ討論会でのバイデン大統領の不出来を受け、「バイデン降ろし」が広がり、今もなお内紛モードが続いている。トランプ・バンスのMAGA系コンビが大統領選を制する可能性が高まっているように見える。
金融市場では、これまで先送りが続いていたFRBの利下げが9月にも開始されることへの期待が高まっていたが、11月大統領選挙でトランプ氏が勝利した場合、インフレ期待を醸成しかねない政策が取られるリスクが高い。果たして2025年は利下げ継続が可能なのか。それが今回のWeekly Economic Reportのテーマである。
図表を含む全文はこちらをクリックしてご覧ください
PDF (約1MB) *新しいウィンドウが開きます
BNPパリバ証券 河野龍太郎: ヒトはいつ、どこでヒトになったのか?-人類の500万年の長い旅路-
No.1060 (2024年7月12日)
今週は国内出張のため、通常のWeekly Economic Reportはお休みし、最近読んだものの中で、衝撃を受けた一冊をご紹介します。以下は、2024年7月6日号の週刊東洋経済への寄稿を修正・加筆したものです。
図表を含む全文はこちらをクリックしてご覧ください
PDF (約1MB) *新しいウィンドウが開きます
BNPパリバ証券 河野龍太郎: QTとQEの非対称性について -超円安は膨らんだバランスシートの副作用なのか-
No.1059 (2024年7月5日)
中央銀行は大規模な資産買入(LSAP : Large Scale Asset Purchase)、すなわちQEを行う際、その効果は絶大であると喧伝してきた。一方で、QTを行う際、その引締め効果は殆どないように振舞っている。日本銀行は、長期国債購入の減額を金融政策と切り離して行うとしているが、金融引き締めと位置付けていないのは、FRBなど他の中央銀行も同様である。QEに緩和効果があって、QTに引き締め効果がないというのは詭弁のようにも見えるが、筆者は、QTとQEは非対称だと考えている。それはなぜなのか。その日本へのインプリケーションは何か。それが今回のWeekly Economic Reportのテーマである。
図表を含む全文はこちらをクリックしてご覧ください
PDF (約1MB) *新しいウィンドウが開きます
関連リンク
日経ヴェリタス「債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」エコノミスト部門首位、債券アナリスト部門8位を獲得
チーフエコノミスト 河野 龍太郎が2022年度優秀フォーキャスターに選定 – 「ESPフォーキャスト調査」における高い予測精度が評価

「成長の臨界」を考えるためのえりすぐりの書籍を紹介しています